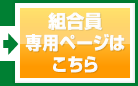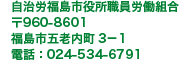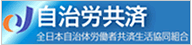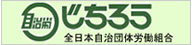春闘から確定闘争へのたたかい
自治労は、「公共サービス労働者総体の賃金を底上げし、社会的な横断賃金の形成をめざす取り組み」を主体的に進め、政策制度を柱に労働を中心とした福祉社会の実現をめざし、官民が連帯して取り組むこととしました。
市職労のとりくみ
市職労は、自治労方針に則り、組合員の生活と権利を守り「安心して働き続けられる職場」の実現と生涯にわたる豊かさを確保し、総合的生活改善を勝ち取るため、公務員連絡会・自治労本部・県本部の提起する全ての統一行動・集会等に積極的に取り組むことを基本にたたかってきました。
2010春闘ハンドブックを作成し、全組合員に配布しながら、春闘方針を2月8日開催の職場委員会で決定し、職場委員を中心に春闘討論学習会を開催したほか、春闘ワッペン、一人1要求、などの取り組みをしました。3月25日を回答指定日とし、3月2日には春闘要求書を当局に対し提出しました。要求書は、[1]基本賃金の引き上げ、[2]所定労働時間7時間45分の4月1日からの速やかな実施、[3]臨時・嘱託職員の処遇改善、[4]団塊世代の大量退職に伴う採用と欠員補充、[5]労働基準法、労働安全衛生法を遵守した職場環境づくり、[6]2010職場要求の改善、を主な内容としました。
要求実現にむけた回答を引き出すため、3月12日に全国統一行動(早朝29分の時間内くい込み集会)を取り組みました。
3月25日の団体交渉では、当局より賃金・労働条件の改定にあたっては、福島県人事委員会勧告を基本に人事院勧告を参考とし、国・県の実施状況等を勘案して措置する考えであり、従前の労使慣行を尊重し対処したいとの回答が示されました。その中で、時間外労働時間の短縮やメンタルヘルス対策については、職員の健康管理の観点から当局に使用者としての責任を果たし、実効性ある対策を施すことを確認しました。また、新給料表の速やかな改善と是正については困難としながらも、新庁舎の執務環境・厚生関連施設や休憩時間の確保については、意見や実態を把握し、十分に協議を重ねて対処していきたいという回答を示しました。さらに、今春闘で連合・自治労の掲げた非正規職員の処遇改善も重点課題とし、具体的には、子育てをはじめとした生活支援のための休暇新設と時間単位の取得を要求しました。交渉の中で市職労は、「市がすすめる小学生までの医療費無料化等は子育て支援策として評価を得ています。市役所も一事業所としての視点で捉えれば、本要求は市の姿勢に十分合致し、新年度より率先垂範して行うべき」と主張し、当初交渉は難航しましたが、最終的には当局は要求を受け入れ、「生活支援休暇」を2010年度から創設することとしました。
市職労は、この回答を春闘段階での一定の成果と判断し、今後迎える人勧期、確定期へ向けた諸要求の前進、さらなる市職労への結集と取り組みの強化を確認しました。
市職労女性部のとりくみ
女性部は、市当局への要求書に、職場における真の男女平等を求める内容を盛り込むとともに「第17回自治労青年女性中央大交流集会」などに参加し、他単組の仲間と交流しながら、2010春闘の課題について学習し、分散会を通じて職場・生活実態について討論し、たたかう意思統一と連帯を確認しました。
さらに、春闘勝利に向けて補助機関三部の意思統一を図るため、今年も女性部・青年部・現業協による「三部合同学習会」を2月24日・25日に開催し、「労働組合の実態と今後にむけて」「10春闘」について学習しました。充実した学習会にするために今後も多くの参加を呼びかけます。
2010確定闘争のとりくみ
1.人事院は、8月10日、国家公務員給与に関し、月例給を平均757円、0.19%引き下げるとともに一時金を0.2月引き下げ、1963年以来の低水準となる3.95月とするという内容の給与勧告を行いました。月例給の引き下げについては、[1]55歳を超える職員について、俸給及び俸給の特別調整額の支給額を一定率(1.5%)で減額し、[2][3]による解消分を除いた残りの公務と民間の給与差を解消するよう引き下げ(平均改定率0.1%)。その際、中高齢層(40歳台以上)が受ける俸給月額に限定して引き下げ、としました。同時に、月60時間超の計算における法定休日(日曜日等)の参入についても勧告しました。
勧告は、民間賃金実勢の反映とはいえ、公務員の生活に大きな影響を与える厳しいものであると同時に、地域の賃金相場と地域経済に悪影響を及ぼすことが懸念され極めて不満な内容であるといえます。50歳台後半層給与については職務級原則や能力実績主義など、この間人事院自身が主張してきたことと矛盾し、給与構造改革の検証や民間給与の詳細データなどの根拠を公務員連絡会に示さないまま勧告を強行したことは認められるものではありません。
2.10月4日に県人事委員会は、[1]55歳超かつ6級以上の職員給与・管理職手当ての0.9%カット(給料表の改定は行わない)[2]一時金について0.15月削減し、年間3.9月とする勧告を行いました。
月例給・一時金については、8月の人事院勧告を上回る史上最悪の引き下げであり、民間賃金の実勢を反映したものとはいえ、公務員の生活実態を無視した極めて不当な勧告であるといえます。55歳超の職員について、給料表及び給料の特別調整額(管理職手当)の支給額を0.9%減額することは、単に国の人事院勧告に追従したものに過ぎず、国と県の違いを無視した勧告と言わざるを得ません。
3.市職労は自治労の秋季確定方針に基づき、10月29日を回答指定日として10月6日当局に対し、「職員の生活を維持・防衛するための賃金水準を確保すること。特に、国・県を下回る給与改定は行わないこと。」「一時金については、支給月数の維持・改善を行うこと。」「高齢層職員や級を限定した給与削減措置を行わないこと。併せて、年間調整を行わないこと。」「職員の健康増進・維持に配慮し、安全確保に向けた労働条件・職場環境の改善を行うこと。特にメンタルヘルス対策についてはリワーク制度の確立を含め、早急な対策を講じること。」等を柱とした統一要求書を提出しました。
当局は今年度の給与改定について、10月27日の事務折衝において「県人勧準拠を基本とする」との姿勢から、[1]県人勧に準拠し、55歳を超えかつ行政職給料表6級以上の職員について、給料及び給料の特別調整額(管理職手当)の支給額を一定率(0.9%)減額する、[2]12月期の期末手当を0.10月、勤勉手当を0.05月引下げ、現行の2.10月を1.95月とする(年間:現行4.05月→3.90月)、[3]給料の引下げ改定に伴う年間調整を行う(0.9%)、との考えを示しました。
加えて、現業統一要求で求めていた現業職員の新規採用については、現段階では困難との回答に終始しました。市職労は、2010秋季確定闘争と現業統一闘争を一体化させたなかで取り組みを進め、10月29日には統一行動を配置し早朝時間内集会を行い、同日午後、団体交渉に臨みました。この団体交渉で、まず現業協から適正な人員配置や経験・知識の豊富な職員の活用・育成等の要求を行いました。これに対し当局側も概ね前向きに検討していきたいと回答しました。さらに市職労は今後も現業職員の新規採用を協議することを回答書に記載することを求め、粘り強い交渉の末、今後も採用について回答書に明記させることができました。一方、本年給与改定については、これらを阻止し、職員の生活を維持・防衛する賃金水準の確保に向けて、今後も交渉を積み重ねることとしました。
その後、11月4日の事務折衝において当局は、給与の引き下げ改定に伴う年間調整を行うための調整率を当初の0.9%から0.86%に引き下げる旨の回答を示しました。年間調整に伴う減額調整率は引き下げられたものの、今回の勧告によって一時金の支給月数が4月を割り込むなど、生涯賃金の大幅な落ち込みになることは明確であることから、全職員に対し12月勤勉手当に職務加算2%上乗せを求めることとしました。
11月12日の団体交渉では、[1]月例給については県人勧に準拠し、55歳を超えかつ行政職給料表6級以上の職員について、給料及び給料の特別調整額(管理職手当)の支給額を一定率(0.9%)減額する、[2]一時金についても県人勧準拠とし、12月期の期末手当を0.10月、勤勉手当を0.05月引き下げ、現行の2.10月を1.95月とする(年間:現行4.05月→3.90月)、[3]給与引下げ改定に伴う年間調整を行うための減額調整率を0.86%とすることを確認しました。しかし、市職労が要求した全ての職員に対して12月期勤勉手当に職務加算2%上乗せを行うことについて、当局は当初難色を示しました。
これに対し市職労は、市民福祉向上のため日々職務に励んでいる職員、とりわけ、給与構造改革以降昇給が行われていない現給保障者に対し、勤労意欲を喚起するためにも何らかの措置を実施すべきとした市職労の要求を当局に受け入れさせ、12月一時金で独自の賃金改善を行うことで合意しました。
また、時間外勤務手当については2011年4月1日から月60時間の超過勤務時間の算定基礎に日曜日又はこれに相当する日の勤務を含めることや、更なるメンタルヘルス対策の強化も確認しました。
以上の交渉妥結をもって、今年の秋季確定闘争を終了しました。
今後も、継続課題の要求実現や、現行賃金の水準確保に向け、総力をあげ取り組みを強化していかなければなりません。