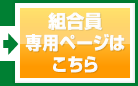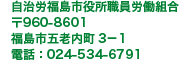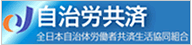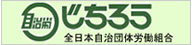男女共生社会の実現と職場の真の男女平等を実現させるために
2007年4月1日に改正男女雇用機会均等法が施行されました。今回盛り込まれた、男女双方への差別禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益扱いの禁止や間接差別の禁止を具体化するための取り組みを進める必要があります。この間、雇用の機会による女性差別禁止など表面的には規制がされてきているものの、賃金・労働条件など雇用形態による新たな差別が起きています。1999年に成立した男女共同参画社会基本法を受け、女性がひとりの人間として尊重され、あらゆる権利が守られ、人間らしく生きられる社会の確立のために、また、男女がともに子どもを産み育てながら家庭的責任を果たしていける職場をつくるため、私たち公務の職場から、男女平等と家庭と職場の調和を推進していく必要があります。
1.今年度の採用状況をみると33名の採用に対し、女性職員は13名と39.4%になっており、2000年以降女性の採用が増えてきたことは、長年取り組んできた目標である、雇用における男女平等の観点からは評価できるところです。今後も男女の枠に捕われず個々の能力に応じた、募集・採用が行われ、女性が不利にならないような取り組みを続けていく必要があります。
2.昇格や研修についての差別は少なくなってきていますが、職場における女性と男性の役割分担は解消されておらず、また女性の職務経験を積み上げる機会が少ないのも事実です。
これからも女性自身が職業人としての自覚と誇りを持ち、働き続ける決意とその権利を守るため、組織の団結を強めていかなければなりません。
3.長年、「扶養手当・諸手当」の是正を要求してきましたが、1999年確定において住居手当における世帯主の認定基準が改正されました。さらに、2002年寒冷地手当の世帯主の認定及び子の扶養手当の認定について追求し、改善されたところです。
引き続き、男女差の是正を要求していきます。
4.「男女共同参画社会基本法」の成立を受け、福島県においては、2002年3月に男女共同参画社会に関する条例が制定され、当市においても、2002年12月27日「福島市男女共同参画推進条例」が施行されました。女性部が長年取り組んできた男女平等の要求は、女性部運動の重要な柱のひとつです。しかし、この要求は生活習慣や社会習慣に根ざしたものが多く、理解を得るのが難しい課題であり、法的な裏づけが求められていました。これらの法律や条例の施行は、保守的意識が根強い中で課題が多く残されているものの、真の男女平等推進の環境づくりへつながるものと期待されます。
今後も、女性部では課題をもって男女平等推進を取り組み、女性自身の意識改革とエンパワーメントを獲得するため、学習・討論を重ねていかなければなりません。