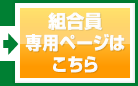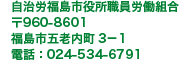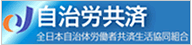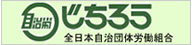地方自治を確立するたたかい
政府主導で進められている市町村合併や規制緩和・アウトソーシングの動きや、三位一体改革による地方財政の逼迫、指定管理者制度・市場化テスト、さらには公務員制度改革など、私たち自治体職員をとりまく情勢は職場・賃金・身分とあらゆる方向から締め付けがされています。地方分権の名の下に行われているこれらの政策は、コスト削減・財政赤字解消を題目とした公務労働者への合理化攻撃を隠れ蓑に、国や地方の借金を、社会保障の負担増・公共サービスの低下という形で住民に押し付けるものでしかありません。
自治体における賃金・労働条件は労使交渉を前提として決定されるものの、条例化にあたっては議会における力関係にも左右されます。矢継ぎ早な賃金削減・合理化攻撃を受けている今、私たち自治体労働者は、地方議会の場に組合員の意見や考えを反映させることを目的とした政治方針を掲げ、追求する必要があります。生活・職場実態は、労働法制改悪などの地方行革・合理化攻撃と密接に関連しており、真の地方自治・地方分権を確立し私たちの生活や権利を守るためには、国政や地方議会の場に組織内議員・支持協力関係にある政党議員を選出する取り組みを進めなければなりません。
青年部では、県本部・県北総支部の提起する反行革・反合理化についての講演や交流集会・労働学校等に参加してきました。その中で、政府・資本が進める合理化政策は、財政締め付けにより地方自治を後退させると同時に、私たちや住民を切り捨てるものだと言うことを学びました。また、総決起集会等に参加し、なぜ政治闘争が必要なのか学習を深めてきました。
◎第22回参議院議員選挙のとりくみ
◇経過と情勢
第22回参議院議員選挙は、6月24日公示、7月11日投票で行われました。
昨年8月30日に行われた第45回の衆議院議員選挙で歴史的な政権交代を果たし、鳩山内閣が誕生しました。しかしその後の「政治とカネ」の問題、「普天間基地移設問題」などで迷走を続け、それに伴い支持率も著しく低下し、ついに6月4日に総辞職しました。鳩山首相の退陣を受け、選挙の顔としても期待され6月4日の衆参本会議において首班指名された菅首相は、就任にあたって「第三の道」を掲げ「強い経済、強い財政、強い社会保障」の実現を打ち出しました。このような情勢下で行われた第22回参議院議員選挙は、政権交代の意義と民主党政権の評価が問われる選挙となりました。
市職労では、昨年12月22日開催の第72回定期大会において、第22回参議院議員選挙を取り組むにあたっての方針を決定しました。具体的な候補者名については、比例代表選挙は、自治労組織内候補者である「えさきたかし」を推薦決定しました。また、県選挙区選挙は、4月8日の連合福島、4月9日の自治労県本部での推薦決定に従い、5月14日に開催された執行委員会において「ましこ輝彦」を推薦候補者として取り組むことを決定しました。
◇具体的なとりくみ
比例区では、連合組織内においても、各産別・構成組織が独自候補者を抱え支持拡大を図っていることから、福島市内では「えさきたかしの獲得票数」が「市職労の獲得票数」を示すこととなりました。このことから、参議院議員選挙は、市職労そのものの力量が問われる選挙であり、市職労の団結力と行動力を内外に示すたたかいと認識しなければなりませんでした。
また、選挙区選挙については、比例区とセットでの支持者拡大に取り組むこととしました。
[1] サポーターカードによる「1組合員6人の紹介」による支持拡大の取り組み
[2] 各種集会への積極的参加
[3] 教宣・オルグ活動の強化
[4] 補助機関等による学習会の開催、政治意識調査の実施
◇青年部のとりくみ
青年部は、市職労方針に沿って各種集会に積極的に参加し、青年層の支持の再確認に努めました。 また、6月24日に市民会館において開催した第4回青年部幹事会において、講師に丹治英之書記長を招き「労働組合と政治闘争の目的と参議院選挙の意義について」と題し講演を受け、今参議院議員選挙の重要性や問題点を確認し取り組みを強化することとしました。
また、執行部方針の周知徹底、政治意識の活性化、さらには、政治課題の掘り起こしを目的として、同じ補助機関である現業協、女性部とともに政治意識調査に取り組み、その結果を踏まえ、終盤における上乗せ行動に取り組むこととしました。
◇たたかいの結果
選挙の結果、市職労の推薦する「ましこ輝彦」は県選挙区においてトップ当選を果たし、「えさきたかし」も民主党内候補者で10位の得票数で当選し、ともに当選を果たすことができました。しかし、民主党は解散議席54を大きく下回り、44議席にとどまる惨敗でした。
民主党敗北の主な要因は、鳩山政権時代の「政治とカネ」の問題、「普天間基地移設問題」によって政権基盤が揺らいでいた上に、菅首相の「消費税増税」発言が国民に違和感と唐突感を与えたためと推察されます。
組織内候補者の「えさきたかし」は133,248票を獲得し、初当選を果たしました。しかし、得票数は3年前の第21回参議院議員選挙における「あいはらくみこ」の得票数を大きく下回り、過去4回の自治労組織内候補の比例代表選挙と比較しても、最も少ない得票となりました。市職労でも同様に、市内の得票数が3年前の「あいはらくみこ」の得票数を大きく下回り、1,000票を割り込む結果となりました。候補者名を記載する「非拘束名簿方式」という複雑な選挙制度や、与党・民主党への逆風などの諸要因はあるものの、市職労の方針や候補者名が職場や家族にまで浸透しきれなかったと反省せざるを得ません。
これらの取り組みを通し、市職労青年部は、「なぜ政治闘争に取り組むのか」「なぜ組織内・推薦候補が必要なのか」について学習を深めるとともに、闘争を通じての組織強化につなげることができました。今後ともこれらの学習・討論を深めるとともに、私たち労働者の意見・考えを議会の場に反映させるため、職場・地域から政治闘争に精力的に取り組んでいく必要があります。
また、私たち青年の要求を自治労の政治方針に反映させるため、生活・職場実態の点検から青年の意識をとらえる取り組みを進めるとともに、国会や地方議会で私たち労働者の代弁者となりうる候補者を見極め、公務員バッシングなどのマスコミ報道に扇動されない確固たる姿勢で政治闘争に取り組まなければなりません。
◎福島県知事選挙のとりくみ
◇経過と情勢
10月14日告示、10月31日投票で行われる福島県知事選挙にあたり、自治労福島県本部では、連合福島及び県職連合での推薦決定状況を踏まえ、10月4日の中央執行委員会(持ち回り)において「佐藤ゆうへい」氏の推薦決定を行いました。そして、10月9日に開催された県本部第87回定期大会において、必勝に向け単組・総支部・県本部が全力でたたかっていくことを確認しました。
市職労もこれらの経過を踏まえ、県本部方針に沿って同氏を推薦決定することとしました。
◇具体的なとりくみ
[1] 教宣・オルグ活動の強化
[2] 各種集会への積極的な参加
◇たたかいの結果
今回の選挙は、現職と新人の候補者2氏による一騎打ちとなりました。
「佐藤ゆうへい」候補は、民主、自民、公明、社民の4党の県組織のほか、連合福島などの労働組合や各種団体の支援を受けました。これまでの4年間の実績に加え、「活力」「安全と安心」「思いやり」を柱とした県総合計画の実現を掲げ、低迷する県内経済の再生など経済対策の充実などを訴えました。結果、県民の立場での県政確立を求めた、労働界を含む多くの県民の支持を得て、「佐藤ゆうへい」候補は有効投票数の88%にあたる609,931票を獲得する圧倒的な勝利を飾りました。
しかし、今回の選挙は共産以外の各党が現職を支援した実質的な「相乗り」で、大きな争点もなく、有権者の関心は高まらなかったためか、投票率は戦後19回の知事選で最も低い42.42%となりました。
今回の勝利は、市職労が追及する住民本位の県政確立の支持を高め、市職労運動も前進させる結果となりました。市職労は、来年の統一自治体選挙の福島市議選において、自治労組織内市議会議員の「たかぎ克尚」の推薦を決定しており、今回の知事選挙で得た多くの支援・支持をさらに拡大していく必要があります。