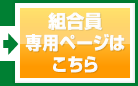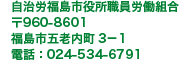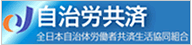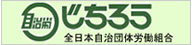2010現業統一闘争
(1) 情勢
国や自治体の財政難を理由とした公務員人件費削減の圧力はきわめて高く、「骨太方針」や集中改革プラン等による総人件費削減や非正規化が地方自治体で進んでいます。そうした状況下、現業職場はとりわけ厳しい合理化の波にさらされています。この動きを象徴するものとして、総務省は08年4月、「技能労務職員の給与に係る基本的考え方に関する研究会」を立ち上げ、8月22日には公務労協・自治労の再三の抗議にもかかわらず「中間とりまとめ」を一方的に公表しました。09年3月19日に出された最終報告では、職務内容の十分な分析と労使交渉を経ての労働協約締結が示されるなど、公務労協・自治労側の最低限の要求は入れられているものの、行(二)の援用や賃金センサスを使用しての水準算出など不満な点も残り、当局に悪用されかねないものとして警戒が必要なものとなっています。
この間の集中改革プランの実施に伴い、PFI、指定管理者制度、独立行政法人、市場化テストなどの法改正を伴う合理化が進められ、自治体業務の民間委託が進む中、現業労働者の退職者不補充、欠員不補充、これまでの技術・技能・経験が生かせない職場への配置転換や行政職への任用替えが行われ、現業労働者の職場が奪われるとともに技術の継承が途絶えるなど、公共サービスは崩壊の危機を迎えています。また、現業職場において臨時・非常勤等職員やアウトソーシングによる公共民間労働者が増加する一方、十分な処遇改善が行われてこなかったため、「官製ワーキングプア」などの言葉にも見られるとおり、きわめて劣悪な賃金・労働条件のもと、公共サービスを現場で支える仲間が働かざるを得ない状況も生じています。09年5月に成立した「公共サービス基本法」の主旨に基づき、公共サービス労働者全体の処遇改善に向け、正規・非正規あるいは公・民などの立場を越えた運動への結集と取り組みが求められます。
(2) たたかいの基本的考え方
自治労本部は、2009年の統一闘争の総括を踏まえ、地域公共サービスを確立する闘争としての位置づけを明確にしながら、全国での取り組み体制の強化を図りました。
2010現業・公企統一闘争のヤマ場の設定については、秋季闘争全体の中に位置づけた上で、10月29日を闘争基準日とし、確定闘争が一層効果的なものとなるようその前段に配置し、取り組むこととしました。 そして、基本的な目標を「現業職場の直営堅持と市民との連携による、自治体の責任に基づいた質の高い公共サービスの確立」とし推進を図ることとしました。また、「[1]公共サービスの拡充と質の向上に向けた人員と予算を確保し、現業・公企職場の直営を堅持する。[2]職場に誇りを持って働くことにより、サービスの質と仕事の価値を高める。[3]地域公共サービス職場労働者の組織化を推進し、労働諸条件についての全体の底上げを図る。[4]地域の中で住民に接する機会の多い現業・公企職場の特性を活用し、市民との協力関係を構築する。[5]現業・公企労働者の協約締結権を活用した取り組みが地方公務員の労働基本権回復後の運動に先導的役割を果たせるよう、要求提出・交渉実施・協約締結という基本的な取り組みを確立する」ことを取り組みの指標としました。
また、現業職員の知識や経験を当局に認めさせることで、その職員の活用のあり方と職員の採用を求めることとしました。さらに、委託業者の適正な労働条件確保と環境整備を求め、全体の底上げを図り、賃金比較の論理に対立軸を求めていくこととしました。
(3) 統一行動の進め方について
[1] 学習会の開催 10月18日 ホテル聚楽
[2] 幹事会で意思統一を図り、執行委員会に反映させる
[3] 要求書提出 10月6日
[4] 団体交渉の強化 10月29日
[5] 教宣活動(すくらむ)の強化
[6] 全職場オルグ 10月21日・22日
(4) 行動日程について
| 月日 | 時間 | 行動内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 10月21日 | 9:00~17:00 | 執行委員会・合同執行委員会 現業協第10回幹事会 全職場オルグ |
市民会館 〃 全職場 |
| 10月22日 | 9:00~17:00 | 全職場オルグ | 全職場 |
| 10月28日 | 15:00~17:00 | 執行委員会・合同執行委員会 現業協第11回幹事会 |
市民会館 〃 |
| 10月29日 | 8:00~17:00 | 統一行動 集約執行委員会・合同執行委員会 現業協第12回幹事会 団体交渉 |
拠点職場 市民会館 〃 〃 |
(5) 現業統一要求書・職場改善要求書提出
現業協は、各部会で職場改善要求の集約を行い、第8回幹事会で現業統一要求について協議し、要求書を作成しました。
現業統一要求書・職場改善要求書は、基本要求とともに10月6日に、基本組織四役と三浦議長が当局に提出しました。
[1] 現業統一要求書
[2] 職場改善要求書
[3] 各部会からの職場改善要望書
(6) 団体交渉
10月29日の団体交渉において、各部会からの改善要望を訴えました。
[清掃部会]
発言者 吾妻清貴(清掃指導係)
発言内容 「清掃指導係の増員とあぶくまクリーンセンターのストックヤード拡張と防犯設備の設置」について
[用務部会]
発言者 塩生 学(吾妻支所)
発言内容 「災害時に即応するための地域リーダーとなる新たな職制の配置」について
[給食部会]
発言者 佐々木 富美(大波小学校)
発言内容 「親子料理教室の開催」について
[運転・一般部会]
発言者 紺野 安彦(維持補修センター)
発言内容 「新庁舎における維持・管理体制と維持補修センターの休日勤務体制・道路110番の設置」について
職場改善要望書の発言を受けて、当局からは一定の理解を示す回答を引き出すことができました。
【清掃職場】
清掃指導員については、「パトロールの強化及び関係機関との連係を図る上で、再任用職員の活用を含め増員を検討する。また、環境教育については教育委員会と連携しリサイクル対策会議で検討していく」としました。
ストックヤードについては、「拡張は困難であるため、別途対策を講じる。シャッターについては不法投棄防止対策として協議したい」としました。
【用務職場】
用務職の新たな職制の配置については、「学校用務職が地域と積極的に関わることで、災害時の連携が図れると思う。そのための、地域リーダーとなる職制については、今後用務職の配置のあり方を踏まえ検討していきたい」としました。
【給食職場】
「親子料理教室」の開催については、「福島市においても、食育を推進しているところであり、市民の関心も高いと認識している。親子料理教室の開催にあたっては、生涯学習課・学習センターとの連携等を含めた体制づくりの支援を前向きに検討したい」としました。
【運転・一般職場】
新庁舎における人員体制・作業場の確保については、「現在のボイラー技師に替わる維持・管理体制は必要であると考える。作業場については、必要性を精査して今後検討したい」としました。
維持補修センターの休日勤務体制と道路110番の設置については、「市民からの通報・要望については、休日のみとは限らず夜間もあるため、全てに対応する交替勤務体制は困難である。また、国交省で既に『道路110番』を設置しており、連絡体制は整っているため、充分である」としました。
このように、今回の交渉において、一部前進ある回答を引き出せたことは一定程度の成果を得られたと言えます。
しかしながら、現業の新規採用については、退職手当債発行の条件であることと、再任用職員の職場確保を理由とし、今年度の採用は厳しいとの回答に終始しました。その一方で、「委託に向かない職場があることは認識している。また、将来的に年齢構成が偏り労務管理も困難になる。状況を見極めながら総合的に判断したい」としました。
執行部は、当初回答書に「採用」についての記載が無かったため、それを明記するよう追求しました。当局は難色を示しましたが、粘り強い交渉の末、採用について今後も協議することを回答書に明記させることが出来ました。
このことは、2012年の労働基本権回復後、回答書・協約書の一言一句が重要なものとなるため、今回明記させたことは、交渉の場で協議することを確約させたことになり、将来に繋がる成果といえます。
これらを踏まえ、今後も市職労・現業協は、現業職場の直営堅持と質の高い公共サービスの確立を目指し、新たな政策を訴え採用に繋がるよう、取り組みを強化します。
(7) 全職場オルグ
10月21日と22日に執行部と現業幹事が一体となって、10.29統一行動への結集と現業統一闘争の理解を求めてオルグを行いました。
(8) 教宣活動(すくらむ)の強化
現業統一闘争の結果と現業問題への理解と協力を、紙面を通じて伝えるため、市職労教宣部とともに「すくらむ」を10月21日、29日及び11月2日に発行しました。
(9) 10.29統一行動(現業統一闘争)のとりくみ
[基本目標]
「現業職場の直営堅持と市民との連携による、自治体の責任に基づいた質の高い公共サービスの確立」
「2010秋季確定闘争の諸要求の前進」
「現業賃金合理化阻止、欠員・退職者補充」
[統一行動日] 10月29日
[闘争戦術] 早朝時間内集会(8:15~8:59)各給食センター(8:00~8:29)
[闘争職場] 本庁、飯坂支所、吾妻支所、信夫支所、松川支所、飯野支所、あぶくまクリーンセンター、あらかわクリーンセンター、維持補修センター、東部・南部・西部・北部学校給食センター、保健福祉センター、下水道管理センター 計15拠点職場