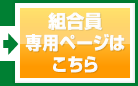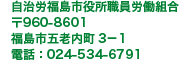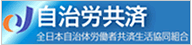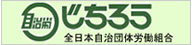用務職場改善
(1) 用務職の職務内容について「環境整備に関する業務」と「管理運営に関する業務」の2点を柱として、学校教育法施行規則第49条の「学校用務員は、学校の環境整備その他の業務に従事する。」という条文を支所・学習センター・保育所など各用務職に置き換え、活性化に取り組んできました。
私たち用務職員は、より安全で利用しやすい施設管理と環境整備を目的として業務に従事していますが、施設設備の近代化と高度化によって業務の範囲は拡大し、これらに対応する知識と技術の向上が求められています。さらに、私たちが勤務する施設の多くが災害発生時の避難場所に指定されています。災害発生時、市民・住民が安心して避難できる施設管理と安全で迅速に避難誘導を行える態勢づくりが重要です。そして、学校の枠を越え、支所・学習センターや地域自主組織との連携を図り避難誘導・安否確認等を行うため、情報管理システムの構築が重要です。私たちは、安易な人員削減や民間委託を許さないためにも、用務職員自ら意識改革を行い、現場から制度政策を提言できる体制を確立しなければなりません。そして、その取り組みのなかで用務職員の位置づけを明確にし、業務の質的向上と職域拡大、強いては職の確立を図ることが重要です。
(2) 全国的に現業職場への合理化攻撃が激しさを増しており、福島市においても支所の統廃合や出張所の廃止により、以前は21施設22名であった支所用務職員がここ10年余りで16施設16名に削減され、管轄地域の拡大により大幅な労働条件の変更を余儀なくされました。また、保育所では、用務職と給食調理職の併任辞令による労働加重などの課題が顕著化しています。そして、新たに学習センター化に伴う勤務・労働条件について検証が必要となっています。このような中、現業協は、労働条件の一方的な変更は許さないという基本理念のもと、仕事量に応じた適正な人員配置を要求してきました。また、合理化させない職場づくりをめざして日常の業務を見直し、効果的に業務が行える体制づくりに取り組んでいます。そのために「[1]学校を含む施設の安全体制を確立すること、[2]危険物取り扱い施設管理要項作成について協議する場を設置すること、[3]職種ごとに作業長の配置を行うことの3点について提起してきました。その結果、危険物取り扱い施設管理要項作成について協議する場が開催されました。今後も要求実現に向け取り組みます。
(3) 市民や職員が気持ちよく快適に利用できる庁舎づくりをめざし、活動委員会の一員として庁舎を花で飾る“庁舎美化ボランティア活動”への参加があります。今年度は7月3日、12月4日の2回にわたり「花の庁舎づくり」にボランティアとして参加しました。現庁舎での活動は今年で最後になりますが、今後、新庁舎移転にともない庁舎美化ボランティア活動の意義や在り方を検証しながら、より快適な庁舎づくりと職員間の交流、そして新たな業務の可能性を模索し、私たちの存在意義をアピールする意味でも活動に積極的に参加していきます。
(4) 学校用務職の実務研修会は、方部制を採用してから今年で11年目となり、通算で15年目を迎えています。現在では全体研修をはじめとして、各方部ごとにテーマを設定し方部研修を実施しています。また、学校以外の用務職(支所・学習センター・保育所・肢体不自由児通園療育センター)の実務研修会も今年で10年目を迎え、知識と技量の向上を目的として実務研修会検討委員会により研修内容や開催時期等を決定し、実施してきました。さらに、実務研修会検討委員が中心となり新規採用職員・職種間異動者に対して、1年間の期限付きで相談員制度を設け、用務職の業務内容や心構えなどについて転入者研修を実施し、よりスムーズな業務の遂行を図っています。
(5) 市の施設には、消防法規定により、「乙種第四類」以上の危険物取り扱い資格者を配置する必要がある地下タンク配管供給施設があり、適正かつ安全な保守管理が求められます。一昨年より引き続き、危険物取り扱い施設の管理要項を作成する「危険物取り扱い施設管理要項作成検討会」を設置し当局と協議・検討を重ねてきました。今後も、各施設の現状や課題を抽出するとともに、より安全で効率的なマニュアルを完成させると同時に、法令に基づいた管理方法を確立するため協議・検討を継続して取り組まなくてはなりません。