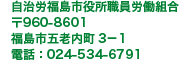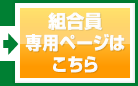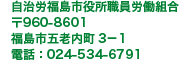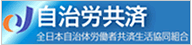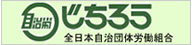沿革(1947年~1959年)
- 1947年(昭和22)
- 4月10日 福島市役所職員組合結成(組合員数342名)
(結成大会を市役所<福ビル>2階会議室で開く)
11月10日 日本自治団体労働組合総連合(自治労連)結成(東京都)
12月22日 自治労連福島県達禽会結成(東京)
- 1948年(昭和23)
- 3月1日 2,920円ベース決定
4月25日 自治労連,福島県連第1回定期大会(郡]」市)
12月2日 5,300円ベース決定
12月8日 人事院発足
12月10日 人事院6,307円ベース勧皆
- 1949年(昭和24)
- 1月 機関紙「市塔」創刊号発刊
4月10日 鴛切行政整理反対街頭署名運動に組合員18名参加
5月1日 第20回統一メーデー
5月13日 組合員総会(定期大会)開催(第一小学校)
6月2日 第一回各課対抗野球大会開催(優勝 教育課)
9月 男女2名の職員に半強制的辞職の勧告でる
10月2日 官公庁44時間制実施
10月14日 地方公務員法、閣議決定
11月28日 自治労連分裂し自治労協結成
12月4日 入事院7,981円ベース勧告(実施されず)
- 1950年(昭和25)
- 1月 物資分配所(売店)開設
1月14日 新春娯楽大会開催
(種目…将模、囲碁、マージャン、カルタ、連珠、羽根つき)
8月9日 人事院8,058円ベース勧告
10月 地域給減廃に対し闘争することを決議
10月 陸上運動会開催
11月21日 7,981円ベースの改正案決定
- 1951年(昭和26)
- 3月12日 総評第2回大会で「平和4原則」を採決
8月20日 人事院11,263円ベース勧告
10月6日 福島県労働金庫認可
- 1952年(昭和27)
- 4月1日 市職員共助会発足
4月1日 本庁舎完成(福ビルから五老内町に移転)
7月1日 衛生課現業職員26名に「雨合羽」貸与
7月 夏季生補金0,5カ月分、超勤手当の完全支給を要求
8月1日 人事院13,515円ベース勧告
10月 「勤務地季当級地引上げに関する請願書」を国会に提出
- 1953年(昭和28)
- 5月6日 第7回定期大会(第二小学校講堂)
7月18日 人事院15,480円ベース勧告
- 1954年(昭和29年)
- 1月3日 自治労統一、全日本自治団体労働組舎結成(松江市)
2月12日 26,000名首切りの行政整理を閣議決定
(以後各自治体で首切りの嵐吹き荒れる)
7月19日 人事院給与改訂不要の勧告
- 1955年(昭和30年)
- 2月 職員26名に対し退職勧告 (4月に更に4名)
4月 退職手当の特別措遺条例案提示
4月 合併地区職員の給与格差是正
4月 林谷革新市政誕生
7月2日 第9回定期大会
7月16日 人事院年末手当0.25月増額勧答
- 1956年(昭和31年)
- 5月1日 第27回統一メーデー (国鉄グランド)
5月 女子職員の被服貸与の予算化に成功
7月8日 占部秀男本部委員長、参院選全国区に高位当選(第12位)
9月8日 第10回定期大会(県労働会館)
9月20日 現業職に黒ズボン支給
1月15日 青年部結成大会
- 1957年(昭和32年)
- 3月3日 第1回市役所スキー運動会
3月29日 婦人部結成大会
3月 教育委員会関係に2名の退職勧告(勧告撤回)
4月5日 第1回自治研全国集会(甲府市)
5月25日 第11回定期大会(第二小学校講堂)
7月16日 人事院年末手当0.15月増額と通勤手当新設勧告
10月 初任給基準の制度化等を要求し、
同一学歴格差給与の是正、制度化をかちとる
(現行賃金制度確立する)
保健婦・看護婦・保母の身分礎立と、調整季当
(資格免許所持者)制度化なる
11月19日 組合休暇制度かちとる

- 1958年(昭和33年)
- 4月 60才以上の退職勧告を白紙撤回
4月 準職員制度廃止(準職員の身分確立をはかる)
2月26日の団体交渉において、準職員30名中、
4月に15~20名正職員昇格を確認
5月24日 第12回定期大会(厚生ホール)
6月 夏期手当1カ月プラスアルファを要求 (0.75カ月プラス500円で妥結
11月 第1回市職自治研集会開催
12月 年末手当2カ月プラスアルファを要求 (1.9カ月プラス1,500円で妥樹
12月 勤勉季当の勤務評定による支給廃止(全員同率支給となる)
12月 公民館職員超勤手当の支給短象となる

- 1959年(昭和34年)
- 2月 自治研荒井集会開催(農政、失対問題で荒井地区住民と話し合う)
4月30日 菅野達夫執行委員長市議選に初当選(第3位)
7月18日 第13回定期大会(厚生ホール)
8月 臨時職員30名を定数化